クラスメイトで、悪友。
関係を位置づけるとしたら、そんなところ。
緑色のドハデな頭。
左耳に、ピアスが三つ。
冷たそうな、怖そうな見た目。どっから見ても、悪そう。
それなのになぜか。近隣の女子高生が、隠れファンクラブまでも作ってるらしい、同級生の男。
ロロノア・ゾロと、
サンジは
友達だ。
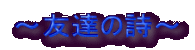
男子校という、ある種 閉鎖された空間。
その中にあって
しかしサンジは 病的に女好きだった。
女の子が大好き。可愛くて、ふわふわしてて、甘いお菓子みたいにいい匂いがする。
見てるだけで幸せな気持ちにさせてくれる愛らしい少女達は、神様がこの世に落とした、至高の清涼剤。
そんな風に 本気で思っている。
のにもかかわらず 今、サンジが唇をくっつけ、あまつさえ舌まで絡ませているのは、
甘くも柔らかくもない、筋肉でがっちがちにコーティングされた でかむっさいマリモ。
(おいおい、青春真っ盛りの高校生っつったらよ、かっわい〜い彼女とか作って、いちゃいちゃラブラブして過ごすのが本分のはずじゃねえのかよ・・・。なにが哀しくて、まわり男ばっかだからって・・・こいつと・・・)
ゾロと、キスをして、性器を触りあいっこしてる、今現在この状況を、
できることなら世界中のレディに泣きながら土下座してまわりたい・・・。
でもたぶんそんなことしたら確実に、おれ羞恥で死ねるな。
死因、恥ずかし死に。 ってなんだそれ。
「おら、なに他ごと考えてんだてめェ。気合入れて扱け」
「うハ、ああぁっ」
口の中に舌を突っ込まれたまま、
ゾロに性器を握りこまれ、ぐりゅ、っと先端に指の腹を押し付けられた。
溢れる先走りで滑る指先が、割れ目に潜り込み、サンジは快感と、少しの痛みにビクビクンと身をすくませる。
「ウア・・ッ、も・と、優しくヤれよ。っ」
「だったら気ィ逸らしてんじゃねぇ」
ほんとに、なんでこんな奴とこんなことしてんのか、自分の正気を疑ってはみるものの。
ゾロに性器を弄られるのは、自分でするより何倍も気持ちいい ということを、毎度のように思い知らされた身であるために、拒絶などもう、出来るはずもなく。
人間、気持ちいいことには弱えもんだ。
うだうだと沸いてくる考えを振り払うと、サンジは再びゾロの一物に指を絡めた。
片手では持ちきれないほど怒張したそれが、ガチッ、と音を立てるかのように硬くなる。
毎回思うんだけども、ゾロのブツは、貴様おれに喧嘩売ってんのか!?と言いたくなるほど無駄にでかい。
そのうえ、達くのも非常に遅いときた。つか、非常識だてめぇのちんこは。
この日も、サンジはもう二回も達したというのに、ゾロのはまだ、たぶん七割ぐらいで。
堪え性ねぇな。と、薄ら笑いでのいつもの台詞も聞き飽きるほど言われて。
(チロウっつーんだおめーのはよ!!)
負けん気根性だけで奮い立ち、扱く手に力をこめた。
後頭部に手を添えられ舌先を擦り合わせながら、性器を刺激し合う。飲み込めない唾液が口端から垂れるのも構わず。
吐き出した白濁を塗られ、ぐちゅん ぐちゅっといやらしい音がするのが、恥ずかしくてたまらない。
「ハ、ぁう、ん・・ア・・ッ」
目に涙をいっぱい溜めて見上げると、目が合ったゾロの屹立が 呼応するかのように跳ねる。先から、ぬめった液が溢れ出してくる・・・。
それが、なんだか嬉しくて。興奮してるゾロを見るのがどうしてだか、楽しくて。
心の中でニッと笑うとサンジは、蹂躙されるだけだった舌先を動かした。
チロチロと、ゾロの分厚い舌を舐める。
だが、仕返しとばかりに口の中を舐めまわされて。
肉厚な、ゾロの舌が、生き物みたいに。
もう それだけでイキそうになる。
「ふあ、ゾ・・ろ、おれ ッも、ダ・・ぃ」
やっと出た言葉が、自分でも思ってた以上に、やけに甘ったるく響いて。
何度もゾロの名を呼びながら
量も色も薄くなった三度目の放出をサンジが迎えると、同時に、
ゾロの、熱くて勢いのよい飛沫が、サンジの腹にぶちまけられた。
「うお ぉぉぉぉぉい筋肉バカ!おまえなにしてくれてんだーー!」
独特の青臭い匂いのこもった部屋で
サンジは制服のシャツをべっとりと汚しながら、ゾロに悪態をつきまくる。
せーえきって洗ってもなかなか落ちねえんだぞ?!
だれが洗濯するとおもってやがんだおれだぞ!このおれ様がっ、ねっとねとになったシャツを、せかせか洗わなくちゃなんねえだなんて間違ってるだろそう思うだろ?!
っつか手で受け止めきれる量を出しやがれ絶倫マリモ!!
とかなんとか。
それに、返すゾロのほうも不機嫌そうに。
「俺の状態見てからもの言えよ」と。
言われて見遣れば、
ゾロの方こそ、悲惨としか言いようのない状態になっている。
三回分のサンジの放出と、ゾロのも混じって、
べっとり、 どころか、 ぐっちゃぐちゃ。
腹にも胸にも飛び散っている粘ついたどちらのものとも知れない体液を、
指ですくうとゾロは、サンジに見せ付けるようににやりと笑いかけた。
「俺は、このまま帰るんだろ」
「・・・・・・っ!!帰るなああああああああ!!!!!」
むがあああばかああああああ と真っ赤になって蹴倒してやりたいのを我慢すると
素早くゾロのシャツを脱がし、急いで濡れたタオルを用意し
ごしごしと乱暴に擦りながら拭いてやる。そのついでに自分も服を脱ぎ、綺麗にしてからトレーナーに着替える。
ゾロにも、着替えを出してやる。これで何着目だか分からない。
いいかげん、貸した服返しやがれっと言ってやると
お前こそ、そのトレーナー、俺んだぞ。と
ズボンも下着も脱ぎ捨て、ぶかぶかの服一枚を羽織った姿に、目を細められる。
ケモノのように紅く滲む瞳に気圧され、腕をとられて
そしてまた、キスをする。
こんなことになったきっかけは、なんだったか。
たぶん、興味本位でサンジから言い出したように思う。
・・・いや?ゾロからだったっけ?
そんなことすら既に曖昧で、もう思い出せない。
学校では、極めて普通の友達同士を装い、
気が向いたときに、どちらかが、『寄ってくだろ』と誘いかける。
学校帰りに、どちらかの部屋で、気の済むまで触りあう。
そのほとんどは、レストランを経営しているサンジの家で。家族が居ないほうが都合がいい。
こんなの、ただの処理とかわんねえだろ。
そう思いながらも、なにか引っかかる部分もありはしたが。
とにかく、ゾロとサンジは、友達で
お互いの性器を弄りあうまでの仲だった。
*************** ****************
それから 十年がたつ。
この十年の月日を、ひとことで言えば、あっというま だった。
高校を卒業し、調理師の専門学校に入り、
決められたことのように祖父のレストランを継ぐ のかと思いきや、
専門学校時代に学んだカクテルに嵌まってしまい、
今は、郊外でバーの経営をしている。
サンジ、二十八歳。
卒業式以来、ゾロには 会っていない。
そもそも、連絡をとろうと思っても、サンジは、ゾロの連絡先を知らなかった。
その当時、携帯電話も普及しだしたばかりで、友達のうちの誰も持っていなかったし、
バイトをしていない貧乏学生がもてるものでもなかったし、
必要性も 感じなかった。
だってそこに 行けば会えたのだ。毎日。
学校という 特別な 場所で。
あの頃は、それが特別なことだなんて気付きもせずに。
店は、サンジ一人で賄っている。
ようやく最近軌道に乗り始め、常連客も安定してきた。
広告すら出していないものの、人づてに聞いて訪れてくれる客もいる。
カウンターが十席と、テーブルをいくつか置けばいっぱいになってしまうほど小さな店だが、
サンジはこの店を、とても愛していた。
ピカピカに磨き上げたグラスを、ひとつひとつ確認しながら、
カウンターの隅に飾られた花を愛でながら、
ときおりサンジは胸に、きゅぅと締め付けられるような痛みを覚える。
たまに、ほんとに、ごくたまに。
胸痛の原因である昔の友人のことを思い出す日があるのだ。三日にいちどくらいで。
高校の卒業式の日、
じゃあまたな、と言って別れたきり、会わなくなってしまった男のことを、懐かしく。
どこか甘く、切なく。
日々の忙しさに追われ、疎遠になってしまったのもあるが。
連絡なんて、ほんとは、とろうと思えばいつでもとれた。
会おうと思えば、その気になればすぐにでも会えるのかも知れない。
だけど、そうしなかった。
(約束なんて、しなかったもんな・・・)
一歩社会に出てしまえば、知らなかった色んな世界が見えてくる。
いくら男子校でも、普通は男同士で、友達同士で弄りあいっこなんてしない。
ってゆーかキスすらしない。
ってゆーか、なんかおかしくなかった?あの関係って。
ということに、卒業してから薄々気付いたサンジが。
男ばかりの世界から解放されて、悔しいがモテるらしいあの男が、いつまでもおれに関わるわけねえよな。と。
思ってしまえば連絡などとれるわけもなく。
だって、理由がない。
二人で会えば、いつも、あんなことしてて。その前まではなにやってたかなんてもう、思い出せないのに。
サンジから、会おうぜ、と誘えば、イコール、しようぜ、と言ってるも同然なのだ。
その関係に陥らせたのはお互い様で、自業自得だけど。
もし、普通の、関係だったなら、今でも友達でいられたのかもしれない、と思うと。
だから胸が痛い。
切なくて、寂しくて、
もう会うこともないだろうと漠然と感じているからこそ、
過ぎ去ったことを。
今は、ただ懐かしむ、それだけだ。
*************** ****************
平日の夜、そこそこに入っていた客もだいぶん引けたころ、
カラン、とドアベルのなるほうに顔を向けた。
条件反射で「いらっしゃいませ」と笑顔で言おうとして、
ま、の口で止まる。
この目で見たものが信じられず、
サンジはぽかんと呆けたように口を開けたまま、入り口に立つ男を見つめ続けた。
緑色のドハデな頭。
左耳に、ピアスが三つ。
冷たそうな、怖そうな見た目。どっから見ても、悪そう。
なんでこんな無愛想な男がモテるんだろう、と悔しく思ってみた時もあった。
十年経って、十年分、凄みを増した容貌。
体格も比べ物にならないほど逞しくなり、男らしい、という形容詞がよく似合う。
いつも胸に思い描いていた、
二十八歳のロロノア・ゾロが
そこにいた。
隣に、鮮やかなオレンジ髪の 女性を連れて。
呆けてしばらくのうち。
カウンターに座った一組のカップルを前に、サンジはようやく気を取り直した。
「・・・久しぶりだな」
こちらも驚いているようなのを見ると、ゾロとてサンジが経営している店だと知って来たわけではないのだろう。
にしても、こんな偶然があっていいものか。
あ、ああ・・と曖昧に返事を返すサンジと、ゾロを、
連れの女性が不思議そうに見比べる。
「なに?ゾロのお知り合い?」
健康的な、抜群のプロポーションの美しいレディに尋ねられて
サンジは見えている右側の目をピンクのハートに変えながら
「そぅおーなんですよ麗しいレディーーvv」っと脂下がった。
サンジにとってレディへの賛辞は日常茶飯事だが、それに慣れていない女性は、怪訝な顔で数十センチ後ろに身を引く。
「高校んときのツレだ」
サンジの代わりに短く返すゾロに、気を悪くした風もなく、
女性は自らを、ナミと名乗った。
こいつはこういうヤツだ、と言うゾロの言葉に、ナミも諦めたのか、
その後のサンジによる愛の言葉の数々は、ことごとくあしらわれた。
ゾロと、楽しく昔話に花を咲かせることなんて、出来るはずもないとは思っていたが。
男女の二人組に、あれこれと詮索してはならない、それはもてなす側の最低限のマナーであったので、
ゾロとナミ、二人の関係を サンジのほうから聞くことはできなくて。
しかし何を話せばいいのかも分からず、つい余計なことをぽろっと言ってしまいそうなのもあり、
自然、話すのは他愛もないことばかりだ。
同級生のあいつが結婚した、だの。
だれそれが家を買ったらしいぞ、とか、
ウソップんところはもう三人目が産まれたらしいぞ、だとか。
ほとんどが、共通の知人の近況だったが。
そんなことを、話す、あいだも。
注文される酒を、次々と腹へおさめるゾロを、ずっと見続ける。
グラスを持つ手つきだとか、
長く節くれだった指先だとか
酒を傾けたときの 喉の動きだとか
飲み干した後、舌で唇を舐める仕草、だとか・・。
おれ、この手に、なんども・・・
あのころに、気持ちがトリップしそうになるたびに、ぐん、と覚えのある熱が腰あたりに宿りそうになって、
ぎゅっと目を瞑って、考えを振り払う。
サンジがふぃっとゾロから目を離した隙に、ゾロもサンジを見返す。
お互いに、目を合わすことはしないまでも、意識しているのはバレバレで。
それを、ゾロの隣のナミだけが、
ふぅん? と面白そうに目を眇めて見ていた。
途中で、他の客が入ってきたので、そちらの相手もしていると、
ゾロとナミは席をテーブルに移し、なにやら話をしていた。
その、二人の距離が、友人というには近すぎる気がして。
親密な関係にしか見えなくて。
サンジはちらちらとそちらの様子を窺う。接客にも、まったく集中できない。
(ゾロの、彼女、だよな、やっぱり・・・)
そうであってもおかしくはないだろう。
もう二十八だし。いい大人だし、やつも男だし、なにしろゾロは誰が見てもかっこいいし。
彼女ぐらいいてもおかしくない。
それに胸を痛めるほうが、
ゾロが左手に指輪を嵌めていないことに安堵するほうが お門違いなのだ。
その距離に、以前いたのは、サンジだった。
ゾロの隣に、いたのは、サンジで、
もしかしたら、今も、居れたかもしれない場所なのに。
手放してしまったことを、悔しいと。
寂しいと思うこの気持ちが、間違い。
いつも感じるものよりも、数段痛みを増す胸の辺りを押さえながら、サンジはその日、
グラスを二つほど落として割った。
―――――なんでこんなに、気になるんだろう。
閉店後の店内で、
片付けも終わり、あとは帰路につくだけで。することもなくなったというのに、
サンジはカウンターに座り、一人酒を呑みタバコをふかす。
結局、碌に話もできなかった。
十年ぶりに会えたのに。
連絡先すら残さず、無言で去っていった男。
「ああ・・・胃が痛え・・・」
胃っていうか、もっと上のほうっていうか。
でもその痛みの原因になんて気付きたくない。考えたくない。
グラスに残ったカクテルを喉の奥に流し込む。
うまい、とも思えず。なのにまたシェーカーを振る気にもなれなくて、ジンをそのままグラスに注いだ。
この店にサンジが居る、と知って、ゾロは、また足を運ぶ事があるだろうか。
もう 来ないかもしれない、なんて思って、傷つく自分がイヤだ。
(・・・傷ついてんのか、おれぁ・・)
ゾロが女性連れだったことに?
ほとんど話せぬまま帰ってしまったことに?
ゾロにとっては、取るに足らない昔の出来事として、片付けられているかもしれないことが?
サンジだって、この年だから、お付き合いした女性も何人かいた。
大人なのだから、ちゅうしたりとかもしていた。
だけどいつも、なんか違う、と思ってしまうのだ。
ゾロの唇を、あの感触をどうしても、思い出してしまう。そうして、いつもそこから先に進めない。
それが何故なのか、自分でもよく分からないけれど。
・・・離れなければよかった。
あのとき、次に会う約束をしていれば、こうも長く思い続けることもなかったのに。
なにもないまま、卒業してしまったから
いつまでも引きずることになるのだ。十年も。
こんな、わけの分からない気持ちを。
ガヅン! ガコン カラン
深夜、物思いにふけったままのサンジの耳に届いた音に。
びくうっと音のしたほうを振り返る。
その瞳に、映る、闇とともに現れた、緑髪の男の姿。
「よう、まだ開いてるか」
鷹揚に尋ねる、その手には、
もぎ取られたドアノブ。
「ゾロ・・・っ!」
サンジは、立ち上がると、そちらに駆け寄り
「ドア壊すなボケがあああああああああああ!!!!!」
勢いよく飛び蹴りをかました。
まあ、軽く受け止められたんだけれども。
「おまえは、ちっとも変わってねえな」
がっちりと掴まれた片脚もそのまま、反転して壁に押し付けられる。
「はな・・離せっ!」
じたじた暴れてみても、微塵も振りほどけない。
触れたところが、火傷するほど熱くて、ゾロが近くて、心臓が、どうにかなりそうなのに。
「離すかよ。また逃げんだろうが」
ずいと顔を近づけられて、また胸が、跳ねた。
「逃げる、って・・また ってなんだよ。」
逃げた覚えなんて、ない。まったく。
睨みつけると、ゾロは不機嫌そうに眉をしかめる。
はぁ、と溜め息を吐いて見下ろされる。
その顔に、なぜか、ふきゅ、と身を竦めた。
「おまえ、ひとりか?・・・ナミさんはどうした?」
「あ?タクシーで帰した。あいつが居たら、話になんねえからな。」
そう言われて、ずきん、と痛みが走る。
もしかして、口止めしに来たとかかな。バッカだなぁ、言うわけないのに・・・。
やっぱり、いくら無頓着なゾロでも、恋人に聞かれたくはないんだろうな、おれとのことを。
「安心しろよ、誰にも言わねぇから・・・」
「・・・は?なにを。」
ずるずると、力を抜いたサンジの脚を放し、ゾロは憮然と問いかける。
言いにくいことを聞きやがって、とは思ったが、ここはきっちり話をつけなければ。
「口止めに来たんだろ、おれとゾロが・・、高校んときにしてたこと。」
「・・ああ。セックスか」
「せ・・・ッッッ!!!」
臆面もない言い方に、サンジの顔が真っ赤になった。ぎに゛ゃ!と喉をつぶしたような声まで出た。
「ちが、ちかうだろ!せ、ックスとかじゃねえだろあれは!それぁ、あれだろ、愛しのレディとするもんであってな!つか入れたり入れられたりするのがアレでな!おれとお前のアレは、あれだ、た、ただのカキッコとかそーゆーもんだろうが!!」
どかああああっと赤くなってあわあわと手を振りながら、やたらと『アレ』を連発するサンジの顎を、ゾロの大きな手で掴まれ、上向かされる。
「だから、そうだろうが、おれとお前のも。入れてねえだけで」
むがあああああ
「違うっつーんなら、もう一回やってみっか」
ひぎゃああああああああああ
あまりの話の通じなさに、眩暈がしそうだ。
ゾロに支えてもらってないと、そのまま床にくず折れそうだった。
・・・・・・支え ・ ・ ・
「ってどさくさでどこ触ってんだおめええぇぇぇええええぇぇえ」
片腕をサンジの腰に回し、
きっちり着込んだスーツのベルトを外そうとするゾロに、今度こそ、何本か頭の血管が切れ、
サンジの意識が少し飛んだ。
よし、お前ちょっとそこ座れ。
んで、順序よく話せ。おれにも分かるように。日本語で!
冷たいおしぼりを額に当てながら、ふらふらとサンジが言い、ゾロは言われた席に腰を下ろす。
その隣の椅子に腰掛け、サンジは、数回深呼吸してから、ゾロに尋ねた。
一体なにしに戻ってきたんだ。何か理由があるんだろ?あんなに可愛いナミさんほっぽりだすなんてよっぽどだろ、おめぇ彼氏の風上にも置けねえぞ?と。
已然、顔を顰めたままの男に。
「ナミ?あいつは、ただのツレだぞ。つか、あいつの相談受けてただけだ」
その不貞腐れたような顔は、昔とちっとも変わってなくて、
ゾロの言葉に、やけにほっとしている自分。
そうかそうか、彼女じゃねえのか。
よかった。
・・・ん?よかったって何だ? と一瞬よぎったが気にしない。
こうしてると、十年も会ってなかったなんて嘘みてえ。
あの頃に戻ったみてえだな。などとくすぐったく思いつつ。
カウンターに肘をつき、ふっと笑うと、ゾロにジロリと睨まれた。
(久しぶりに会う友達に、その顔はねえだろうよ。)
思ってみても、無表情よりはよっぽどマシか。
「あ、なあ。さっきの、『逃げる』ってなんだ?おれが、いつゾロから逃げたよ?」
つか、自分達のやってたことをセックスだと断言されたことのほうが気にかかるが、そこはあえて突っ込むまい。
話を掘り返すと、ゾロは渋々、といった風に
「俺は、言ったよな。お前に、突っ込みてエって。」
「・・・・・ ? 」
「卒業式が終わったら、俺んちに来い、つって、お前は来なかった。」
「・・・・・・・・・・・・ん?」
カク、と首を傾げた拍子に手から顎がずれる。
「昔の話だ。もう忘れろ」
「・・・・・・ゾロ、 ゾロ?」
「あんだ」
「 言われて ませんけど?」
「・・・ああ!?言っただろうが。」
「いいいいいつだよ!?知らねえぞおれぁ!!夢ん中か妄想か?!てめぇフカシこいてんじゃねえぞウラァ!」
イラついたように言うゾロに、サンジが喰らいかかる。
ゾロのシャツの胸元を掴んで揺さぶると、うざったそうにその手を取られた。
「嘘ついてどうする。・・・お前ほんとに、覚えてねえのか?」
じっと見つめられて、サンジのぐわーーっと上がったテンションが、しおしおと下がる。
あれ?なんか、冗談じゃないっぽいぞ?と。ゾロの視線に、責められているような気持ちになってバツが悪い。
うん・・・と頷いて上目で見遣ると、ゾロは呆れたようにでかい溜め息をつき
「俺の十年返せ・・・」
と彼らしくもないことを呟いた。
頭の血管もう二、三本どっか行きそうになりながら、ゾロから聞いたことと、サンジの記憶を
纏めて要約すると
卒業間近のある日
いつものようにサンジの部屋で
イキすぎてぐでぐでになったサンジに、それでもまだ全身弄くりながらゾロが先ほどの台詞を吐いた。
その頃にはもう、お互いの局部を触りあうだけでは済まなくなってて
事あるごとにゾロはサンジの体を触ったり舐めたり、揉んでつねって引っ張ってまた舐めたりしていたが
なにをしても甘い声を上げしかもそこらじゅうピンク色に染めてるサンジがもうどうにもアレで。
そのうえたぶん入れる用には出来ていないそこをゾロが弄ったり舐めたりしても、サンジも嫌がる素振りも見せず
突っ込みてえ、と思うがまま言ったら、サンジは素直に頷いた。
いいよ、ゾロ・・と。嬉しそうな顔で。それを見てゾロも堪らず達した。
でも何の用意もなかったためにその日は挿入に至らず
卒業式が終わったら、お前を抱く、と言い切って、そしてまた弄くり倒した。
サンジがぐちゃぐちゃになって泣き喚いてもうやだと言うまで。
そして、サンジは 今の今まで
きれいさっぱり忘れてた。
(つーかよ、そんな時に言うなってんだ。意識トンでて何言われたかなんて分かっちゃねえっつの)
憤慨しながらも、悪い気は全然しなくて。むしろ嬉しくて、幸せで。
ああ、ゾロに言われたんなら、おれはたぶん頷いたんだろうな〜と、どこか遠くで思う。
で、今日のこともまた忘れたらどうしよう。
と不安に思って、圧し掛かるゾロに言ってみると、
意識飛ばさねえ程度に手加減してやる。と既にけっこうトロトロにされながら言われた。
十年、誰にも触らせていない体は、思ったよりすんなりとゾロを受け入れた。
何度も、何度もその精を受け止めながら、
好きだ、好きだと、考えるよりも先に言葉にしていた。
抱き合って、溶け合って、隙間をふさぐように。
会わなかった十年という期間を埋めるように。
想いを育てるために、必要な時間だったのかもしれないと、サンジはなんとなく思う。
あの頃に、気付けたかもしれない、気付かなかったかもしれない、この気持ちを。
無駄にはしないと、もう二度と、離れたりしないと、
固く胸に誓い、ゾロを抱き締めた。
結局、ゾロが何をしに店に戻ってきたのかを、その口から聞くことはできなかったが。
店のドアノブが外れているため、いつ誰に覗かれてもおかしくない状況だった、ということにサンジが気付くのと、
ゾロからあやすようなキスを受け、俺も好きだ、という十年越しの告白が聞けたのは
翌日、日がどっぷり暮れた後だった。
そして
CLOSEDの看板を、
ゾロがしれっと出していたことに 気付くのも。
E n d
「あくあまりん」のまりのさんへ、お誕生日プレゼントと称して捧げさせていただきましたv
目指せシリアス!! そして撃沈。(笑)
自覚なしなだけで、やってることはラブラブ、なゾロサンができあがりました・・・
まりのさん、お誕生日おめでとうございましたv
お読みいただいた皆様ありがとうございましたーv
雪城さくら
ブラウザを閉じてお戻りください