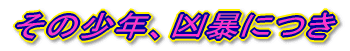父親に、「会わせたい人がいます」と言われたとき、
十二歳のゾロは、ただ黙って頷いた。
母親が亡くなってから十年、男手ひとつで育ててくれた父だった。
道場の経営と、ゾロの世話。働き通しで、自分の趣味を楽しむ時間もなかっただろう。
それでも、弱音など一切吐かず、何不自由なく、育ててくれた。
そろそろ、父も、幸せになってもいいと。
そう思って。
小学校の卒業式を終えた三月の初め。
ゾロの住む町の外れにあるレストランへと、父に連れて行かれた。
進学の決まっている公立中学の制服を着て。
まだ幼さの残る顔立ちに、少し緊張した、けれど大人びた表情を浮かべて。
たぶん、ここで、新しく母親になる女性に会うのだろう。
どんな人だろうか。父を、愛してくれている人は。
・・・優しい人だといい。
優しく穏やかな父に似合いの、ふわりと微笑む女性をおぼろげながらに想像して、ゾロの鼓動は高まった。
しかし、父とゾロが通された席には、先客はおらず、
席につくと同時に運ばれてくる料理も二人分で。
少々訝しげに
「父さんの、相手って、どんな人?今日ここに来るんじゃないのか?」
訊きながら、父を見遣り、驚いた。
「いいから、食べてください。おいしいですから」
そう言う父の表情は、見たこともないほどに幸せそうで。
うっすらと頬を染めてまでいる。
「・・・うん」
小さなレストランではあれど、それらの料理は、食べたことがないほどに美味かった。
料理に対するうんちくは、ゾロにはさっぱりだったがそれでも、シェフの腕のよさがうかがえる。
懐かしく。新しく。なんだか、暖かくなる味。
なんとか星レストラン、とかの味は、きっとこんなんだろう。行ったことはないが。
「うまい!すげぇ美味いよ」
「でしょう?」
思ったまま料理を褒めると、何故か父のほうが、照れたような、それでいて誇らしそうな顔をする。
その表情に、ゾロはやっと気付いた。
「この料理を作ったひとが、父さんの相手か?」
ふふ、と眼鏡の奥の細い目をさらに細め、静かに頷くのを見て。
ああ、こんな顔を父にさせてくれる、とても素晴らしい人なんだろうな、と。
それだけでもう、父の再婚に、諸手をあげて賛成したい気分だった。
「一通りのコースが終わったら、ここに来ることになってますから」
やけに嬉しそうな父の言葉に頷き、出された料理を全てたいらげた。
今は食事はゾロの当番だけれど、美味しい、とお世辞にも言えないような代物しかまだ作れないし、 中学からは部活も始まる。
新しく母親になるかもしれない人物が、飯が美味いとくれば、言うことなしだ。
いや、飯のためではないが、毎日うまいものが食えるに越したことはない。
その人が来たら、『父さんをよろしくお願いします』と、言おうと思っていた。
誰よりも優しい父だから。二人で、幸せになってください、と。
しかし、
デザートも終わり、食後のコーヒーを飲んでいるときに、
自分達の前に現れたのは、
どう見ても、イカついオッサン。だった・・・
「・・・・・・とうさん・・・・このひと、が」
「そうですよ」
父の迷いのない返答を呆然と反芻し、
目の前に立ったままの、コックコートを着て、口元にヒゲを・・・
・・・ヒゲかどうかもいささか微妙な毛をたくわえた、その男性を見あげる。
ゾロの三倍はあろうかという巨体。首が痛くなりそうなほど上を向かなければ、顔が見えないほど。
その上、強面、というより、ソッチの道の人にしかみえない顔つき。
道でばったり会ったら、まず間違いなく、通行人がズザザザザーーーーっと道をあけるだろう、と容易に想像がつく。
父の経営する道場では、同学年どころか、高校生にだって負けないゾロだが。
このときばかりは、肩に入った力を、抜くことができずにいた。
はっきり言って。
恐すぎる。
「とうさん。」
「なんですか?」
「・・・。父さん」
「・・・言いたいことは分かります。驚きもするでしょうね。でもねゾロ、」
「いや、俺が説明する」
少し困惑したような父の言葉尻をとらえ、そのオッサ・・・男性は、険しい顔に、おそらく精一杯の笑顔を浮かべ、
余計に恐い顔になりながら、ゾロに語りかけた。
数年前、出稽古の帰りの父が立ち寄ったこのレストランで初めて会ったと。
年甲斐もなく、一目惚れをしてしまった。
お互い、惚れあっている、ということを知ったときは、奇跡のような思いだった、と。
「苦労はかけない。必ず、幸せにする。」
そう語る男の顔は、とても力強く思え。
嬉しそうに気恥ずかしそうに彼を見遣る、父の顔も、また。
二人の関係を、ゾロは正しく受け止めた。
思っていたような『女性』ではなかったけれど。実際、まだ戸惑いもあるけれど。
きっと、父は彼といて、安らぎと幸せをもらったのだろう。
顔をあげて、
「父さんを・・・よろしくお願いします」
じっと、薄いブルーの瞳を見つめて言った。
「・・・ありがとう。」
そう言って初めて、男は、柔らかい笑みを浮かべる。
「家族四人で、仲良くしていきましょうね、ゾロ」
目に涙を浮かべている父を見るのも、初めてだ。
やっぱり、これでよかったんだ。父さんが、幸せなら。
「ああ。・・・・・・・・・・四人・・?」
ギョッとして、父の恋人 −と思って差し支えないだろう− に目を向けると。
今まで気付かなかったのもどうかしているが、
彼の足元に、大きな体に隠れるようにして、こっそりとこちらを覗きこんでいる少年がいた。
丸っこい頭で、金の髪の、何故か眉毛がぐるんと二巻きほどしている、
少年、というにはあまりに小さいその坊主が・・・
ものすごい、形相で、ゾロを睨んでいる・・・
ぐるるるるるる。と唸り声をあげんばかりに。
「俺のせがれの、サンジだ。来年で三年生になる。少々人見知りでな・・」
・・・人見知り、というのか、これは?
どう見ても、親の敵を睨んでます状態。喉の奥からは、猛獣の発する警戒音に似た音まで聞こえる。
「可愛い子でしょう?ゾロの、弟になるんですよ。」
しかし、爽やか過ぎるほどにこやかに父に言われ。
可愛い。ということについてはなんとも言えなかったが、とりあえず頷いておいた。
「よろしくな、サンジ。おれはゾロだ」
しゃがんで、目線を合わせると、そいつの瞳も、薄い青色なのが見てとれる。
驚くほどまん丸に目を開いたそいつは、目の前に差し出されたゾロの手を、
いきなり がぶぅっっっ!!!と噛んだ。
あまりに突然で、予想もしていなかった事態。
「・・・・・・・父さん。」
呆然自失に、父を見れば。
「照れてるんですよ。可愛いですねぇ」
「いや。待て。」
救いを求め、父の相手を見遣れば。
「すまんな、ゾロ君。慣れないうちは、こんなもんだ」
「・・・・オイ待て。よく見ろ手。」
「これから、よろしくお願いしますね、サンジ君」
「いや、こっちこそ、よろしく頼む」
・・・・・駄目だこの大人たちは!!!!!
ロロノア・ゾロ、十二歳。
こぢんまりとした、レストランの一角で。
右てのひらを、小さな怪獣に咥えられたまま。
いえいえこちらこそ・・・なんて呑気な挨拶を交わしている父親二人を、愕然と眺めた。
続く・・・・のかどうか。
たぶん続かない(笑)